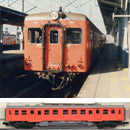下館レイル倶楽部
真岡鐵道・関東鉄道常総線・JR水戸線が集まる「下館」を中心に活動する鉄道模型趣味・鉄道趣味の倶楽部です。(2009年6月12日開設)
【オススメ】KATO「E531系」付属編成セット(5両)
- 2010/05/03 (Mon)
- オススメ(鉄道模型) |
- TB() |
- CM(0) |
- Edit |
- ▲Top
当地・下館界隈を走る鉄道車両の中で、「E531系」にはちょっと複雑な思いを抱いている方が少なくないかも知れません。
「E531系」は、老朽化・陳腐化した「403系」や鋼製「415系」(ステンレス車体を採用した「1500番台」登場までに製造された車両)を置き換えるためにJR東日本が開発・量産した常磐線・水戸線の車両です。
宇都宮・高崎線用、東海道線に開発・量産した「E231系」を進化させた交直両用の電車で、10両の基本編成と、5両の付属編成の、最長15両編成を組成します。
2005年8月に開業し、130km/h運転を行う「つくばエクスプレス」に対抗して、最高運転速度は130km/h。
「E231系」での問題点を踏まえ、さまざまな改良が施され、なかなか完成度の高い形式となりました。
デビュー当初はロングシート車とセミクロスシート車だけでしたが、宇都宮・高崎線に導入したグリーン車が(JR東日本の予想を良い意味で裏切って)とても好評で、じゃあ常磐線にもグリーン車を……ということになったため、途中から10両の基本編成の4号車と5号車は2階建てグリーン車に変更となりました。
さて……。
こうして華々しくデビューした「E531系」が、水戸線にも投入されるとの発表が行われました。
水戸線には5両編成の付属編成(ロングシート車×2、セミクロス車×3)が入ることになるので、これは乗客満足度も高い内容です。
実際に水戸線での「お披露目」運用が始まると、「403系」や鋼製「415系」とは比べものにならない良好な居住性・快適性に、一般の乗客も大満足。
これで水戸線にも少しは明るい兆しが……と思った矢先のことでした。
あろうことか、水戸線には「E531系」ではなく、「E501系」の付属編成が入線することに!!
「お披露目」運用では格上の「E531系」が走っているのに、本運用では格落ちの「E501系」になるというのです。
これには「E531系」にグリーン車が連結されることになったことが背景にありました。
常磐線の上野~土浦間を走っていた「403系」、鋼製「415系」、「415系1500番台」、「E501系」は、全てこの区間から追い出され、土浦までの全列車にグリーン車を連結する、つまり「E531系」に運用を統一することになったのです。
「403系」や鋼製「415系」は、どちらにしても全廃。
「415系1500番台」は、土浦以北の常磐線と水戸線に限定。
「E501系」は改造の上、10両の基本編成は土浦以北の常磐線、5両の付属編成は土浦以北の常磐線と、水戸線に限定。
真新しく快適な「E531系」に慣れてきた水戸線の乗客は、この突然の方針変更をどう感じたのでしょうか……。
従来7両編成の鋼製「415系」で運転していた列車は、5両の「E501系」付属編成での運転に変わりました。
新設されたトイレは、気のせいか他の車両の使い回しのような印象で、全車オールロングシート。
鋼製「415系」よりは快適性が増したとはいえ……がっかりした利用者が多いことは言うまでもありません。
「遠くに行ってしまった」ような感じの「E531系」付属編成ですが、その後「E501系」や「415系1500番台」の代走として水戸線に入線してくることがあり、タイミング良く乗ることができた人は「ラッキー!!」と感じていることは言うまでもありません(笑)。
……というわけで、前置きが長くなりましたが、「KATO(カトー)」からNゲージの「E531系」をモデル化しています。
発売当初は、「基本セット」(8両)と「付属編成セット」(5両)、それに「増結セット」(サハ2両)の3種類でした。当初は車輪のフランジが実車に近い「ローフランジ」仕様でした。
グリーン車の連結が決まると、「増結セット」はグリーン車2両に変更となりました。
その後、KATOが新方針を打ち出し、各地域を代表する車両は入手しやすい商品構成に変え、品切れを起こしにくくするという目的で「ベストセレクション」として展開することに。
現在「E531系」は、
・10-570「E531系常磐線 基本セット(4両)」(税込定価:11,550円)
・10-571「E531系常磐線 増結セットA(4両)」(税込定価:8,505円)
・10-572「E531系常磐線 増結セットB(2両)」(税込定価:3,150円)
・10-283「E531系常磐線 付属編成セット(5両)」(税込定価:14,910円)
の、4種類の商品ラインナップとなっています。
10両の基本編成は、基本セット+増結セットA+増結セットBを揃えると組成できます。
今回ご紹介するのは、水戸線にも入線してくる「付属編成セット」です。
5両編成ですので、そんなに大きなレイアウトでなくても十分見栄えがしますし、「415系1500番台」など他の形式と一緒に走らせることで「水戸線気分」を味わうこともできるかと思います。
老舗KATOらしい、値段と出来映えのバランスが良い製品で、スムーズに良く走ります。
「E531系」は、老朽化・陳腐化した「403系」や鋼製「415系」(ステンレス車体を採用した「1500番台」登場までに製造された車両)を置き換えるためにJR東日本が開発・量産した常磐線・水戸線の車両です。
宇都宮・高崎線用、東海道線に開発・量産した「E231系」を進化させた交直両用の電車で、10両の基本編成と、5両の付属編成の、最長15両編成を組成します。
2005年8月に開業し、130km/h運転を行う「つくばエクスプレス」に対抗して、最高運転速度は130km/h。
「E231系」での問題点を踏まえ、さまざまな改良が施され、なかなか完成度の高い形式となりました。
デビュー当初はロングシート車とセミクロスシート車だけでしたが、宇都宮・高崎線に導入したグリーン車が(JR東日本の予想を良い意味で裏切って)とても好評で、じゃあ常磐線にもグリーン車を……ということになったため、途中から10両の基本編成の4号車と5号車は2階建てグリーン車に変更となりました。
さて……。
こうして華々しくデビューした「E531系」が、水戸線にも投入されるとの発表が行われました。
水戸線には5両編成の付属編成(ロングシート車×2、セミクロス車×3)が入ることになるので、これは乗客満足度も高い内容です。
実際に水戸線での「お披露目」運用が始まると、「403系」や鋼製「415系」とは比べものにならない良好な居住性・快適性に、一般の乗客も大満足。
これで水戸線にも少しは明るい兆しが……と思った矢先のことでした。
あろうことか、水戸線には「E531系」ではなく、「E501系」の付属編成が入線することに!!
「お披露目」運用では格上の「E531系」が走っているのに、本運用では格落ちの「E501系」になるというのです。
これには「E531系」にグリーン車が連結されることになったことが背景にありました。
常磐線の上野~土浦間を走っていた「403系」、鋼製「415系」、「415系1500番台」、「E501系」は、全てこの区間から追い出され、土浦までの全列車にグリーン車を連結する、つまり「E531系」に運用を統一することになったのです。
「403系」や鋼製「415系」は、どちらにしても全廃。
「415系1500番台」は、土浦以北の常磐線と水戸線に限定。
「E501系」は改造の上、10両の基本編成は土浦以北の常磐線、5両の付属編成は土浦以北の常磐線と、水戸線に限定。
真新しく快適な「E531系」に慣れてきた水戸線の乗客は、この突然の方針変更をどう感じたのでしょうか……。
従来7両編成の鋼製「415系」で運転していた列車は、5両の「E501系」付属編成での運転に変わりました。
新設されたトイレは、気のせいか他の車両の使い回しのような印象で、全車オールロングシート。
鋼製「415系」よりは快適性が増したとはいえ……がっかりした利用者が多いことは言うまでもありません。
「遠くに行ってしまった」ような感じの「E531系」付属編成ですが、その後「E501系」や「415系1500番台」の代走として水戸線に入線してくることがあり、タイミング良く乗ることができた人は「ラッキー!!」と感じていることは言うまでもありません(笑)。
……というわけで、前置きが長くなりましたが、「KATO(カトー)」からNゲージの「E531系」をモデル化しています。
発売当初は、「基本セット」(8両)と「付属編成セット」(5両)、それに「増結セット」(サハ2両)の3種類でした。当初は車輪のフランジが実車に近い「ローフランジ」仕様でした。
グリーン車の連結が決まると、「増結セット」はグリーン車2両に変更となりました。
その後、KATOが新方針を打ち出し、各地域を代表する車両は入手しやすい商品構成に変え、品切れを起こしにくくするという目的で「ベストセレクション」として展開することに。
現在「E531系」は、
・10-570「E531系常磐線 基本セット(4両)」(税込定価:11,550円)
・10-571「E531系常磐線 増結セットA(4両)」(税込定価:8,505円)
・10-572「E531系常磐線 増結セットB(2両)」(税込定価:3,150円)
・10-283「E531系常磐線 付属編成セット(5両)」(税込定価:14,910円)
の、4種類の商品ラインナップとなっています。
10両の基本編成は、基本セット+増結セットA+増結セットBを揃えると組成できます。
今回ご紹介するのは、水戸線にも入線してくる「付属編成セット」です。
5両編成ですので、そんなに大きなレイアウトでなくても十分見栄えがしますし、「415系1500番台」など他の形式と一緒に走らせることで「水戸線気分」を味わうこともできるかと思います。
老舗KATOらしい、値段と出来映えのバランスが良い製品で、スムーズに良く走ります。
E531系常磐線 付属編成セット(5両) 【発売】KATO(カトー) 【ジャンル】鉄道模型(Nゲージ) 【発売日】2007年10月19日 【税込価格】14,910円 【備考】「ホビナビ」が半額セール実施中(2010.5.2現在) |
PR
【オススメ】KATO「キハ20」首都圏色
- 2010/05/03 (Mon)
- オススメ(鉄道模型) |
- TB() |
- CM(0) |
- Edit |
- ▲Top
当地・下館界隈を走っていた鉄道車両の一つが、「キハ20系」です。
「キハ20系」は、国鉄時代に全国津々浦々で見ることが出来たディーゼルカーです。
今も県内の「ひたちなか海浜鉄道」では現役で走っている仲間がいますが、これはかなり希有なケース。
すっかり「絶滅危惧種」になってしまいました。
「キハ20系」は、両運転台の「キハ20」、片運転台の「キハ25」をベースに、寒冷地用の両運転台車「キハ22」、車体の半分は郵便荷物車の「キハユニ26」などのバリエーションがありました。
下館界隈では、電化前の水戸線で日中の普通列車に「キハ25」が2両とか3両編成で走っていたようですし、真岡線でも「キハ20」や「キハ25」が走っていました。
国鉄末期には、真岡線から小山駅への直通列車も走っていて、「キハ20系」の普通列車が結城駅で待避線に入り、後続の急行「つくばね」(小山貨物線を通るので小山駅には行かない)と接続を取っていたりしました。
実は関東鉄道常総線の「キハ0形」は、不要となった「キハ20系」の足回りを流用して、車体を新製した車両なんです。
もっとも、デビュー時点で「キハ20系」を感じさせる要素はエンジン音以外にはほとんどなく、その後エンジン換装や冷房改造を行ってますので、現在は天井に設置されている扇風機の「JNR」ロゴが辛うじて残る「痕跡」といえます(扇風機は「現役」/冷房使用時も併用することで冷気を攪拌しています)。
Nゲージでは、もう30年ほど前にKATO(当時は「関水金属」)がバリエーション展開していて、モーターなしの車両は850円(!!)、動力車でも2,800円ほどというリーズナブルな価格設定で、事実上「入門モデル」でもありました。
最近になって、TOMIXがHGシリーズで「キハ20系」を製品化し、細かいディテールも再現。しかし、価格がかなり割高になっています。
KATOの「キハ20系」は、最近のモデルでは標準の前照灯は点灯せず、TOMIXのHG「キハ20系」に比べればディテールはさすがに見劣りします。
しかし、全体的な特徴はちゃんと再現しているし、何よりも昔と変わらない安価なモデルであるというのが最大のメリットです。
初期の生産品では「ディーゼルエンジン積んでるのか!?」と揶揄された(苦笑)盛大な駆動音も、再生産の度にどんどん改良され、今ではとてもスムーズで、全く問題ないレベルです。
今回ご紹介するのは、真岡線でも活躍し、現在も真岡駅構内で静態保存されている両運転台型の「キハ20」首都圏色の動力車(モーター付き)です。
1両で走らせても良いし、ほかの車両と組み合わせて走らせても良いので、1両持っておくと良い車両だといえます。
「ライトが点かないと……」という場合は、たとえば「キハ30系」や「キハ40系」、「キハ52」など、前照灯や尾灯が点灯する車両と組み合わせて、この「キハ20」が先頭にならないようにすれば、本車がライト機能を有しないということはさほど問題にはなりません。
元は古いモデルなんですが、持っていると何かと便利な車両ですし、何より動力車なのに実売価格では2,000円ちょっとで手が届くというお手頃感が魅力の一品です。
往年の真岡線での活躍を思い浮かべながら、1両いかがですか?
「キハ20系」は、国鉄時代に全国津々浦々で見ることが出来たディーゼルカーです。
今も県内の「ひたちなか海浜鉄道」では現役で走っている仲間がいますが、これはかなり希有なケース。
すっかり「絶滅危惧種」になってしまいました。
「キハ20系」は、両運転台の「キハ20」、片運転台の「キハ25」をベースに、寒冷地用の両運転台車「キハ22」、車体の半分は郵便荷物車の「キハユニ26」などのバリエーションがありました。
下館界隈では、電化前の水戸線で日中の普通列車に「キハ25」が2両とか3両編成で走っていたようですし、真岡線でも「キハ20」や「キハ25」が走っていました。
国鉄末期には、真岡線から小山駅への直通列車も走っていて、「キハ20系」の普通列車が結城駅で待避線に入り、後続の急行「つくばね」(小山貨物線を通るので小山駅には行かない)と接続を取っていたりしました。
実は関東鉄道常総線の「キハ0形」は、不要となった「キハ20系」の足回りを流用して、車体を新製した車両なんです。
もっとも、デビュー時点で「キハ20系」を感じさせる要素はエンジン音以外にはほとんどなく、その後エンジン換装や冷房改造を行ってますので、現在は天井に設置されている扇風機の「JNR」ロゴが辛うじて残る「痕跡」といえます(扇風機は「現役」/冷房使用時も併用することで冷気を攪拌しています)。
Nゲージでは、もう30年ほど前にKATO(当時は「関水金属」)がバリエーション展開していて、モーターなしの車両は850円(!!)、動力車でも2,800円ほどというリーズナブルな価格設定で、事実上「入門モデル」でもありました。
最近になって、TOMIXがHGシリーズで「キハ20系」を製品化し、細かいディテールも再現。しかし、価格がかなり割高になっています。
KATOの「キハ20系」は、最近のモデルでは標準の前照灯は点灯せず、TOMIXのHG「キハ20系」に比べればディテールはさすがに見劣りします。
しかし、全体的な特徴はちゃんと再現しているし、何よりも昔と変わらない安価なモデルであるというのが最大のメリットです。
初期の生産品では「ディーゼルエンジン積んでるのか!?」と揶揄された(苦笑)盛大な駆動音も、再生産の度にどんどん改良され、今ではとてもスムーズで、全く問題ないレベルです。
今回ご紹介するのは、真岡線でも活躍し、現在も真岡駅構内で静態保存されている両運転台型の「キハ20」首都圏色の動力車(モーター付き)です。
1両で走らせても良いし、ほかの車両と組み合わせて走らせても良いので、1両持っておくと良い車両だといえます。
「ライトが点かないと……」という場合は、たとえば「キハ30系」や「キハ40系」、「キハ52」など、前照灯や尾灯が点灯する車両と組み合わせて、この「キハ20」が先頭にならないようにすれば、本車がライト機能を有しないということはさほど問題にはなりません。
元は古いモデルなんですが、持っていると何かと便利な車両ですし、何より動力車なのに実売価格では2,000円ちょっとで手が届くというお手頃感が魅力の一品です。
往年の真岡線での活躍を思い浮かべながら、1両いかがですか?
キハ20 首都圏色(動力車) 【発売】KATO(カトー) 【ジャンル】鉄道模型(Nゲージ) 【発売日】2004年9月10日 【税込価格】2,993円 【備考】実売価格は2,000円台前半 |
【関東鉄道】「常総線一日フリーきっぷ」親子割引を実施中
- 2010/05/01 (Sat)
- ニュース(鉄道・LRT・バスなど) |
- TB() |
- CM(0) |
- Edit |
- ▲Top
関東鉄道は、「常総線一日フリーきっぷ」の親子割引を実施しています。
大人1人につき、小学生以下の子ども2名までを無料とする割引キャンペーンで(通常の子ども料金は750円)、期間は2010年4月3日(土)~9月26日(日)の土日祝祭日。
両親とお子さん2人の4人家族だと、大人1,500円×2人分=合計3,000円のみで常総線が1日乗り放題となります。
(通常は子ども料金750円×2人=1,500円が追加となり、家族で計4,500円)
お子さんが3~4人だと、さらにお得感が増します(笑)
・関東鉄道
http://www.kantetsu.co.jp/
・【ニュースリリース】常総線1日フリーきっぷ「親子割引」の実施について(2010年3月24日)
http://www.kantetsu.co.jp/news/100324_freeticket/100324_freeticket.html
・常総線一日フリーきっぷ「親子割引」の実施について
http://www.kantetsu.co.jp/news/100324_freeticket/news.pdf
往復1,500円以上の距離を移動する場合は、迷わず利用した方が良い「常総線一日フリーきっぷ」。
ということは、片道750円以上であれば「元が取れます」。
「下館」駅~「玉村」駅の片道運賃が790円。
「守谷」駅~「玉村」駅の片道運賃も790円。
下館方面から常総線を使う場合、玉村より南(つまり、石下や水海道、守谷、取手など)まで行く場合は「フリーきっぷ」が便利。
守谷方面から常総線を使う場合、玉村より北(つまり、下妻、大宝、騰波ノ江、下館など)に行く場合は「フリーきっぷ」が便利です。
「下館」駅は、「SLもおか」号が走る「真岡鐵道」の始発駅です。当方「下館レイル倶楽部」が定例運転会を行っている「アルテリオ」も、この駅が最寄り駅です。
「大宝(だいほう)」駅を下りると、徒歩数分の場所に古くから戦勝祈願などで知られる「大宝八幡宮」があります。
「騰波ノ江(とばのえ)」駅では、毎月第3週の土日に鉄道模型の展示運転会「とばのえステーションギャラリー」が行われています。
「守谷」駅から「つくばエクスプレス」に乗り継げば、
・「柏の葉キャンパス」駅前の「ららぽーと」
・「流山おおたかの森」駅前の「流山おおたかの森ショッピングセンター」
・「研究学園」駅から徒歩数分の「イーアスつくば」
に渋滞知らずで移動できますし、
・「守谷」駅から徒歩数分の「ロックシティ守谷」
にも行けます。
今の常総線は、運転本数が少なくなる水海道~下館間であっても、日中でも1時間に2本の列車が走っています。
朝夕の時間帯には運転本数はさらに増えますし、朝は下館から守谷方面へ、夕方は守谷から下館方面への快速も走っています。
渋滞必至の連休中だからこそ、列車を上手に活用して出かけてみませんか?
大人1人につき、小学生以下の子ども2名までを無料とする割引キャンペーンで(通常の子ども料金は750円)、期間は2010年4月3日(土)~9月26日(日)の土日祝祭日。
両親とお子さん2人の4人家族だと、大人1,500円×2人分=合計3,000円のみで常総線が1日乗り放題となります。
(通常は子ども料金750円×2人=1,500円が追加となり、家族で計4,500円)
お子さんが3~4人だと、さらにお得感が増します(笑)
・関東鉄道
http://www.kantetsu.co.jp/
・【ニュースリリース】常総線1日フリーきっぷ「親子割引」の実施について(2010年3月24日)
http://www.kantetsu.co.jp/news/100324_freeticket/100324_freeticket.html
・常総線一日フリーきっぷ「親子割引」の実施について
http://www.kantetsu.co.jp/news/100324_freeticket/news.pdf
往復1,500円以上の距離を移動する場合は、迷わず利用した方が良い「常総線一日フリーきっぷ」。
ということは、片道750円以上であれば「元が取れます」。
「下館」駅~「玉村」駅の片道運賃が790円。
「守谷」駅~「玉村」駅の片道運賃も790円。
下館方面から常総線を使う場合、玉村より南(つまり、石下や水海道、守谷、取手など)まで行く場合は「フリーきっぷ」が便利。
守谷方面から常総線を使う場合、玉村より北(つまり、下妻、大宝、騰波ノ江、下館など)に行く場合は「フリーきっぷ」が便利です。
「下館」駅は、「SLもおか」号が走る「真岡鐵道」の始発駅です。当方「下館レイル倶楽部」が定例運転会を行っている「アルテリオ」も、この駅が最寄り駅です。
「大宝(だいほう)」駅を下りると、徒歩数分の場所に古くから戦勝祈願などで知られる「大宝八幡宮」があります。
「騰波ノ江(とばのえ)」駅では、毎月第3週の土日に鉄道模型の展示運転会「とばのえステーションギャラリー」が行われています。
「守谷」駅から「つくばエクスプレス」に乗り継げば、
・「柏の葉キャンパス」駅前の「ららぽーと」
・「流山おおたかの森」駅前の「流山おおたかの森ショッピングセンター」
・「研究学園」駅から徒歩数分の「イーアスつくば」
に渋滞知らずで移動できますし、
・「守谷」駅から徒歩数分の「ロックシティ守谷」
にも行けます。
今の常総線は、運転本数が少なくなる水海道~下館間であっても、日中でも1時間に2本の列車が走っています。
朝夕の時間帯には運転本数はさらに増えますし、朝は下館から守谷方面へ、夕方は守谷から下館方面への快速も走っています。
渋滞必至の連休中だからこそ、列車を上手に活用して出かけてみませんか?
【関東鉄道】2010年5月4日・5日に限り常総線の時刻変更
- 2010/04/30 (Fri)
- ニュース(鉄道・LRT・バスなど) |
- TB() |
- CM(0) |
- Edit |
- ▲Top
関東鉄道は、2010年5月4日・5日の2日間のみ、常総線の運転時刻変更を行うと発表しました。
時刻変更となるのは、下妻 18:04発 → 下館 18:24着の下り列車1本のみ。
両日のみ、下妻 18:12発 → 下館 18:32着に変更となります。
・関東鉄道
http://www.kantetsu.co.jp/
・【ニュースリリース】常総線運転時刻変更のお知らせ
http://www.kantetsu.co.jp/news/100430_traindia/100430_traindia.html
・運転時刻変更のお知らせ
http://www.kantetsu.co.jp/news/100430_traindia/news.pdf
(PDF形式のファイルです)
時刻変更となる理由については記載がありませんでしたし、私には思い当たる節がありませんでした。
そこで、思い切ってニュースリリースに掲載されていた同鉄道の鉄道部運転車両課に問い合わせてみたところ、「例年行っている『定期戦』の団体輸送に対応するためです」とのお返事でした(この点については公開OKとの確認済み)。
その後ちょっと調べて見たところ、下妻駅至近の下妻一高(茨城県立下妻第一高等学校)の恒例行事で、「兄弟校」(下妻一高の公式サイトによる)である水海道一高(茨城県立水海道第一高等学校)との「定期戦」が行われているとのこと。
(水海道一高は、1900年に当時の下妻中学校の「水海道分校」として開校しています)
「ウィキペディア」の「茨城県立水海道第一高等学校」によると、この「定期戦」は下妻一高と水海道一高の運動部による対抗戦で、現在は毎年1回の開催です。
会場は、毎年交互に双方の高校を使用。
試合に参加する各運動部の部員だけでなく、応援のため全校生徒が参加するという大がかりなものです。
この手の団体輸送は、観光バスを使うことが多いような気もしますが、両校とも常総線沿線で、それぞれ駅から近い学校だということも常総線を利用する決め手になっているのかも知れませんね。
下妻は比較的近所なんですが、このような大がかりな交流が行われていることは全然知りませんでした。
私は下館の高校出身なんですが、こうした全校挙げての他校との交流は行われていなかったので、なんだかちょっとうらやましいような気もします。
時刻変更となるのは、下妻 18:04発 → 下館 18:24着の下り列車1本のみ。
両日のみ、下妻 18:12発 → 下館 18:32着に変更となります。
・関東鉄道
http://www.kantetsu.co.jp/
・【ニュースリリース】常総線運転時刻変更のお知らせ
http://www.kantetsu.co.jp/news/100430_traindia/100430_traindia.html
・運転時刻変更のお知らせ
http://www.kantetsu.co.jp/news/100430_traindia/news.pdf
(PDF形式のファイルです)
時刻変更となる理由については記載がありませんでしたし、私には思い当たる節がありませんでした。
そこで、思い切ってニュースリリースに掲載されていた同鉄道の鉄道部運転車両課に問い合わせてみたところ、「例年行っている『定期戦』の団体輸送に対応するためです」とのお返事でした(この点については公開OKとの確認済み)。
その後ちょっと調べて見たところ、下妻駅至近の下妻一高(茨城県立下妻第一高等学校)の恒例行事で、「兄弟校」(下妻一高の公式サイトによる)である水海道一高(茨城県立水海道第一高等学校)との「定期戦」が行われているとのこと。
(水海道一高は、1900年に当時の下妻中学校の「水海道分校」として開校しています)
「ウィキペディア」の「茨城県立水海道第一高等学校」によると、この「定期戦」は下妻一高と水海道一高の運動部による対抗戦で、現在は毎年1回の開催です。
会場は、毎年交互に双方の高校を使用。
試合に参加する各運動部の部員だけでなく、応援のため全校生徒が参加するという大がかりなものです。
この手の団体輸送は、観光バスを使うことが多いような気もしますが、両校とも常総線沿線で、それぞれ駅から近い学校だということも常総線を利用する決め手になっているのかも知れませんね。
下妻は比較的近所なんですが、このような大がかりな交流が行われていることは全然知りませんでした。
私は下館の高校出身なんですが、こうした全校挙げての他校との交流は行われていなかったので、なんだかちょっとうらやましいような気もします。
【富山地鉄】「T100形」運転開始/「サントラム」と命名
- 2010/04/30 (Fri)
- ニュース(鉄道・LRT・バスなど) |
- TB() |
- CM(0) |
- Edit |
- ▲Top
先日当方でも紹介しました富山地方鉄道(富山地鉄)の市内軌道線用の新型LRV「T100形」ですが、4月28日から営業運転がスタートしました。
南富山駅で行われた「発車式」では、この車両の愛称を「サントラム」と命名しています。
・富山地鉄 17年ぶりに LRVサントラムを新製(「路面電車とLRTを考える館」 2010年4月29日)
http://www.urban.ne.jp/home/yaman/news95.htm
・『サントラム』発車 愛称発表 県内初の3連接車両(中日新聞 2010年4月17日)
http://www.chunichi.co.jp/article/toyama/20100429/CK2010042902000186.html
「サントラム」は、愛称公募の結果、最も多かった名称。
3連接の「3」、「ポートラム」「セントラム」に続く富山3番目のLRVという「3」、太陽の「サン」(笑)……等々、まあいろんな意味と思いを込めたネーミングとなりました。
「T100形」は、豊橋鉄道の「T1000形」(ホットラム)と同形で、3連接車体の低床型LRV。
全長 16.3m、車体幅 2.4m、床面の高さは38cm。
購入費は2.4億円で、国・富山県・富山市・富山地鉄がそれぞれ1/4ずつ負担しています。
当面は「南富山」~「富山」間を1時間に1往復する運用で、軌道の整備が進み次第「大学前」までの通し運転が行われる見通しです。
連休中に富山方面を訪れる方は、ぜひこの素晴らしい車両で市内観光をお楽しみください。
南富山駅で行われた「発車式」では、この車両の愛称を「サントラム」と命名しています。
・富山地鉄 17年ぶりに LRVサントラムを新製(「路面電車とLRTを考える館」 2010年4月29日)
http://www.urban.ne.jp/home/yaman/news95.htm
・『サントラム』発車 愛称発表 県内初の3連接車両(中日新聞 2010年4月17日)
http://www.chunichi.co.jp/article/toyama/20100429/CK2010042902000186.html
「サントラム」は、愛称公募の結果、最も多かった名称。
3連接の「3」、「ポートラム」「セントラム」に続く富山3番目のLRVという「3」、太陽の「サン」(笑)……等々、まあいろんな意味と思いを込めたネーミングとなりました。
「T100形」は、豊橋鉄道の「T1000形」(ホットラム)と同形で、3連接車体の低床型LRV。
全長 16.3m、車体幅 2.4m、床面の高さは38cm。
購入費は2.4億円で、国・富山県・富山市・富山地鉄がそれぞれ1/4ずつ負担しています。
当面は「南富山」~「富山」間を1時間に1往復する運用で、軌道の整備が進み次第「大学前」までの通し運転が行われる見通しです。
連休中に富山方面を訪れる方は、ぜひこの素晴らしい車両で市内観光をお楽しみください。
【運転会告知】アルテリオ2010年5月定例運転会
- 2010/04/29 (Thu)
- 運転会開催のお知らせ |
- TB() |
- CM(0) |
- Edit |
- ▲Top
2010年5月の定例運転会のお知らせです。
ご都合がよろしければ、ぜひご参加ください。



【開催予定】
・開 催:2010年5月15日(土)18:00~5月16日(日)16:00(以後、17:00まで撤収作業)
・会 場:しもだて地域交流センター「アルテリオ」2F「研修室」(茨城県筑西市)
http://www.city.chikusei.lg.jp/kurashi/shisetsu/shisetsu/kouryu/kouryu.html
・設営&試走:2010年5月15日(土)18:00~
・夕食懇親会:2010年5月15日(土)21:00頃から
・運転会本番:2010年5月16日(日) 9:00~16:00
・備考1:HOゲージ・Nゲージの周回コースを設置予定です
・備考2:前日設営のみ、運転会本番のみの参加も可能です
・備考3:運転会当日はギャラリーが見物に来ます
・備考4:ご参加の場合、会場費について若干ご支援いただけますと幸いです^^;
【集合】
・前日設営からご参加の場合
……クルマ利用の方は、「アルテリオ」地下駐車場に駐車後、18:00に2F受付前で集合
……鉄道利用の方は、下館駅北口から徒歩5~6分で「アルテリオ」です(道順など不安な方は事前にお知らせください)
今回の会場は、「アルテリオ」2F「研修室」です。
運転会本番は5月16(日)ですが、15日(土)は設営ついでに「夜間走行」もお楽しみいただけるのではないかと思います。
参加ご希望の方は、人数把握の都合上、5月13日(木)までにお申し出くださいますようお願いします。
(本記事にコメントをつけていただくか、「ミクシィ」の「下館レイル倶楽部」コミュニティにて書き込みを行ってください)
なお、当ブログにコメントを付けたい場合は、各記事のタイトル下にある「CM」の部分をクリックすれば、コメント投稿ウィンドウが開きます。
【5月15日・朝~夕方/自由行動】
・真岡鐵道「SLもおか号」乗車
……往路は下館10:37発→茂木12:02着
……復路は茂木14:28発→下館15:57着
……途中の益子(ましこ)駅で下車し、陶芸の街を散策するのも良し
……茂木12:20発→もてぎプラザ12:25着の循環バスに乗って昼食を摂り、もてぎプラザ14:15発→茂木駅14:19着で戻れば、復路の「SLもおか号」に乗車可能
……下館13:00頃発の普通列車に乗れば、復路の「SLもおか号」に乗車可能
・「とばのえステーションギャラリー」見物
……下館から関東鉄道常総線で3駅めの「騰波ノ江(とばのえ)」駅の駅舎内で実施
……開催時間は、15日・16日とも9:00~16:00
……入場無料/レイアウトで運転する場合は10分150円(車両の持ち込みも可)
【5月15日・夜/設営、オフ会】
・オフ会
……1日目の運転会終了後、下館駅周辺(たぶん「フライングガーデン」)で開催
【5月16日・朝~夕方/運転会】
・運転会
……会場は17:00まで押さえてありますが、ラスト1時間は撤収作業です
・真岡鐵道(真岡市公式サイト内)
http://www.city.moka.tochigi.jp/mokasl/
・道の駅もてぎ もてぎプラザ
http://www.motegiplaza.com/
・とばのえステーションギャラリー
http://www.kantetsu.co.jp/train/tobanoe_gallery/tobanoe_gallery.html
(ちょこっと宿泊案内)
・「ホテル新東」
http://www.hotel-shinto.co.jp/
・「ホテル ルートイン下館」
http://www.route-inn.co.jp/search/hotel/index.php?hotel_id=529
ご都合がよろしければ、ぜひご参加ください。
【開催予定】
・開 催:2010年5月15日(土)18:00~5月16日(日)16:00(以後、17:00まで撤収作業)
・会 場:しもだて地域交流センター「アルテリオ」2F「研修室」(茨城県筑西市)
http://www.city.chikusei.lg.jp/kurashi/shisetsu/shisetsu/kouryu/kouryu.html
・設営&試走:2010年5月15日(土)18:00~
・夕食懇親会:2010年5月15日(土)21:00頃から
・運転会本番:2010年5月16日(日) 9:00~16:00
・備考1:HOゲージ・Nゲージの周回コースを設置予定です
・備考2:前日設営のみ、運転会本番のみの参加も可能です
・備考3:運転会当日はギャラリーが見物に来ます
・備考4:ご参加の場合、会場費について若干ご支援いただけますと幸いです^^;
【集合】
・前日設営からご参加の場合
……クルマ利用の方は、「アルテリオ」地下駐車場に駐車後、18:00に2F受付前で集合
……鉄道利用の方は、下館駅北口から徒歩5~6分で「アルテリオ」です(道順など不安な方は事前にお知らせください)
今回の会場は、「アルテリオ」2F「研修室」です。
運転会本番は5月16(日)ですが、15日(土)は設営ついでに「夜間走行」もお楽しみいただけるのではないかと思います。
参加ご希望の方は、人数把握の都合上、5月13日(木)までにお申し出くださいますようお願いします。
(本記事にコメントをつけていただくか、「ミクシィ」の「下館レイル倶楽部」コミュニティにて書き込みを行ってください)
なお、当ブログにコメントを付けたい場合は、各記事のタイトル下にある「CM」の部分をクリックすれば、コメント投稿ウィンドウが開きます。
【5月15日・朝~夕方/自由行動】
・真岡鐵道「SLもおか号」乗車
……往路は下館10:37発→茂木12:02着
……復路は茂木14:28発→下館15:57着
……途中の益子(ましこ)駅で下車し、陶芸の街を散策するのも良し
……茂木12:20発→もてぎプラザ12:25着の循環バスに乗って昼食を摂り、もてぎプラザ14:15発→茂木駅14:19着で戻れば、復路の「SLもおか号」に乗車可能
……下館13:00頃発の普通列車に乗れば、復路の「SLもおか号」に乗車可能
・「とばのえステーションギャラリー」見物
……下館から関東鉄道常総線で3駅めの「騰波ノ江(とばのえ)」駅の駅舎内で実施
……開催時間は、15日・16日とも9:00~16:00
……入場無料/レイアウトで運転する場合は10分150円(車両の持ち込みも可)
【5月15日・夜/設営、オフ会】
・オフ会
……1日目の運転会終了後、下館駅周辺(たぶん「フライングガーデン」)で開催
【5月16日・朝~夕方/運転会】
・運転会
……会場は17:00まで押さえてありますが、ラスト1時間は撤収作業です
・真岡鐵道(真岡市公式サイト内)
http://www.city.moka.tochigi.jp/mokasl/
・道の駅もてぎ もてぎプラザ
http://www.motegiplaza.com/
・とばのえステーションギャラリー
http://www.kantetsu.co.jp/train/tobanoe_gallery/tobanoe_gallery.html
(ちょこっと宿泊案内)
・「ホテル新東」
http://www.hotel-shinto.co.jp/
・「ホテル ルートイン下館」
http://www.route-inn.co.jp/search/hotel/index.php?hotel_id=529
【熊本市電】軌道の片寄せ区間が開業
- 2010/04/29 (Thu)
- ニュース(鉄道・LRT・バスなど) |
- TB() |
- CM(0) |
- Edit |
- ▲Top
九州の話題ですが、先進的な事例ですのでご紹介します。
日本初のLRVを導入するなど先進的な取り組みでも知られる熊本市電。
九州新幹線の全線開業を見据えて行われているJR熊本駅周辺整備事業の一環として、JR熊本駅前の約570mの区間について、これまで道路の中央にあった路面電車の軌道を、駅側の歩道に寄せる「サイドリザベーション」化する(軌道を「片寄せ式」にする)工事が終わり、4月26日の始発から移設された軌道での運行を開始しました。
・熊本市電のサイドリザベーション区間が開業(「railf.jp」 2010年4月27日)
http://railf.jp/news/2010/04/22/175300.html
・JR熊本駅と市電 往来便利に安全に(朝日新聞 2010年4月27日)
http://mytown.asahi.com/kumamoto/news.php?k_id=44000001004270001
・新幹線開業前に熊本市電が軌道を移す 2010年4月27日)
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/kumamoto/news/20100426-OYT8T01327.htm
上記URLの内、朝日新聞の記事には移設された軌道を高所から見下ろす構図の写真が掲載されていて、一目で「なるほど、こう移設したのか」と分かると思います。
写真右手がJR熊本駅で、写真中央に見える白いしゃもじ状の構造物は、JR熊本駅から市電の熊本駅前電停まで、雨や日射を避けるために新設されたコンクリート製の屋根です。
従来は道路を横断しないと電停に行けなかったのに対して、移設後は道路を横断する必要がなく、駅から直接スムーズに移動できるようになっています。
サイドリザベーション軌道は、電停(電車の停留所)が従来のセンターリザベーション軌道(道路の中央に軌道がある)に比べると、電停を自動車交通から切り離すことができるので、乗客の安全性が高まるという効果があります。
今回JR熊本駅前で導入となったのは、軌道の上下線とも片側に寄せる「片寄せ式」でしたが、他に上下線をそれぞれ道路の外側に寄せる「両寄せ式」もあります。
「両寄せ式」は、道路の外側に設けられるバス専用レーンを専用軌道にしたようなもの……と考えるとイメージしやすいと思います。
乗客の利便性が著しく向上するという意味ではベストな選択なんですが、路肩駐車対策や、路肩を使っての荷捌きに影響しないかなど、解決すべき課題が少なからず発します。
(外に寄せた軌道のさらに外側に荷捌きスペースを設けるなど、懸念される不便を解消する対策はあります)
今後、新規にLRT導入を行う都市では、サイドリザベーション軌道の導入を当初から盛り込むのではないかと思います。
私見ですが、もし茨城県つくば市のような道路幅が広い都市であれば、区間によっては「両寄せ式」を採用できるのではないかと思っています。
日本初のLRVを導入するなど先進的な取り組みでも知られる熊本市電。
九州新幹線の全線開業を見据えて行われているJR熊本駅周辺整備事業の一環として、JR熊本駅前の約570mの区間について、これまで道路の中央にあった路面電車の軌道を、駅側の歩道に寄せる「サイドリザベーション」化する(軌道を「片寄せ式」にする)工事が終わり、4月26日の始発から移設された軌道での運行を開始しました。
・熊本市電のサイドリザベーション区間が開業(「railf.jp」 2010年4月27日)
http://railf.jp/news/2010/04/22/175300.html
・JR熊本駅と市電 往来便利に安全に(朝日新聞 2010年4月27日)
http://mytown.asahi.com/kumamoto/news.php?k_id=44000001004270001
・新幹線開業前に熊本市電が軌道を移す 2010年4月27日)
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/kumamoto/news/20100426-OYT8T01327.htm
上記URLの内、朝日新聞の記事には移設された軌道を高所から見下ろす構図の写真が掲載されていて、一目で「なるほど、こう移設したのか」と分かると思います。
写真右手がJR熊本駅で、写真中央に見える白いしゃもじ状の構造物は、JR熊本駅から市電の熊本駅前電停まで、雨や日射を避けるために新設されたコンクリート製の屋根です。
従来は道路を横断しないと電停に行けなかったのに対して、移設後は道路を横断する必要がなく、駅から直接スムーズに移動できるようになっています。
サイドリザベーション軌道は、電停(電車の停留所)が従来のセンターリザベーション軌道(道路の中央に軌道がある)に比べると、電停を自動車交通から切り離すことができるので、乗客の安全性が高まるという効果があります。
今回JR熊本駅前で導入となったのは、軌道の上下線とも片側に寄せる「片寄せ式」でしたが、他に上下線をそれぞれ道路の外側に寄せる「両寄せ式」もあります。
「両寄せ式」は、道路の外側に設けられるバス専用レーンを専用軌道にしたようなもの……と考えるとイメージしやすいと思います。
乗客の利便性が著しく向上するという意味ではベストな選択なんですが、路肩駐車対策や、路肩を使っての荷捌きに影響しないかなど、解決すべき課題が少なからず発します。
(外に寄せた軌道のさらに外側に荷捌きスペースを設けるなど、懸念される不便を解消する対策はあります)
今後、新規にLRT導入を行う都市では、サイドリザベーション軌道の導入を当初から盛り込むのではないかと思います。
私見ですが、もし茨城県つくば市のような道路幅が広い都市であれば、区間によっては「両寄せ式」を採用できるのではないかと思っています。
【KATO】2010年8月の新製品情報
- 2010/04/28 (Wed)
- ニュース(鉄道模型) |
- TB() |
- CM(0) |
- Edit |
- ▲Top
鉄道模型ショップ「ポポンデッタ」のブログ「ポポンデッタ商品部NEWS」に、「KATO」2010年8月新製品情報が掲載されました。
・KATO8月の新製品(EF15最終形etc)お得な先行予約受付開始!
http://popondetta.com/blog/cat1/kato8ef15etc.html
同サイトの掲載情報によると……。
【新製品】
・10-011 スターターセットSP C57「SLばんえつ物語」
・10-828 C57「SLばんえつ物語」基本セット4両
・10-829 「SLばんえつ物語」増結セット(4両)
・3062-2 EF15 最終形
・10-581 E127系0番台 新潟色 2両セット
・10-583 115系1000番台新潟色3両セット
・8037-5 タキ1000日本オイルターミナル色(帯なし・エコレールマーク付)
・10-825 タキ1000日本石油輸送ENEOS(エコレールマーク付)8両セット
【再生産】
・10-298 683系2000番台しらさぎ5両基本セット
・10-299 683系2000番台しらさぎ3両増結セット
・3045 EH200
・8005 スニ40
・8008 タキ3000
・8018-2 ク5000乗用車付
「EF15」は、いずれ複数のバリエーションが発売となるんだろうな……と皆さん思っていたことと思いますので、今後もさらなる展開があるかも知れませんね。
「E127系」と「115系」の新潟車は、予想の範囲内というところでしょうか。
長野に続き新潟……となると、今度はどこだろう? なんて想像もしたくなります。
それぞれの地域を代表する車両を、今後もフットワーク良く継続的に発売していくきっかけになるのでしょうか。期待したいところです。
「SLばんえつ物語」号セットが製品組み替えとなったのは、ちょっと意外。
小分けにすることで、金額的に入手しやすくなったとはいえると思います。
タンク車「タキ1000」の8両セットは、貨物好きには嬉しいラインナップ。
貨物列車というのは、運転会で長大編成にして走らせてみると、とても見栄えがします。
「下館レイル倶楽部」でも、長大コンテナ貨物を走らせたことがありましたが、長大タンク車編成もさぞ壮観だろうと思います。
各ショップでも、近い内に予約受付が始まることと思います。
・KATO8月の新製品(EF15最終形etc)お得な先行予約受付開始!
http://popondetta.com/blog/cat1/kato8ef15etc.html
同サイトの掲載情報によると……。
【新製品】
・10-011 スターターセットSP C57「SLばんえつ物語」
・10-828 C57「SLばんえつ物語」基本セット4両
・10-829 「SLばんえつ物語」増結セット(4両)
・3062-2 EF15 最終形
・10-581 E127系0番台 新潟色 2両セット
・10-583 115系1000番台新潟色3両セット
・8037-5 タキ1000日本オイルターミナル色(帯なし・エコレールマーク付)
・10-825 タキ1000日本石油輸送ENEOS(エコレールマーク付)8両セット
【再生産】
・10-298 683系2000番台しらさぎ5両基本セット
・10-299 683系2000番台しらさぎ3両増結セット
・3045 EH200
・8005 スニ40
・8008 タキ3000
・8018-2 ク5000乗用車付
「EF15」は、いずれ複数のバリエーションが発売となるんだろうな……と皆さん思っていたことと思いますので、今後もさらなる展開があるかも知れませんね。
「E127系」と「115系」の新潟車は、予想の範囲内というところでしょうか。
長野に続き新潟……となると、今度はどこだろう? なんて想像もしたくなります。
それぞれの地域を代表する車両を、今後もフットワーク良く継続的に発売していくきっかけになるのでしょうか。期待したいところです。
「SLばんえつ物語」号セットが製品組み替えとなったのは、ちょっと意外。
小分けにすることで、金額的に入手しやすくなったとはいえると思います。
タンク車「タキ1000」の8両セットは、貨物好きには嬉しいラインナップ。
貨物列車というのは、運転会で長大編成にして走らせてみると、とても見栄えがします。
「下館レイル倶楽部」でも、長大コンテナ貨物を走らせたことがありましたが、長大タンク車編成もさぞ壮観だろうと思います。
各ショップでも、近い内に予約受付が始まることと思います。
【秩父鉄道】武州荒木駅と「1000系」電車
昨日(2010年4月25日)、墓参のため埼玉・行田市へ出かけてきました。
雲一つない晴天で、この季節らしい暖かさが戻る絶好の日和でした。
墓参には我が家と故人の後輩達が参加。
我が家はクルマで出かけ、先日数年ぶりで連絡が取れた故人の後輩の1人を秩父鉄道・武州荒木駅でピックアップし、お寺へ向かう段取り。
途中、朝食を仕入れたりトイレ休憩したり、買い物したりしながら、合流地点の武州荒木駅には、11:20過ぎに到着。
実際に訪れるのは初めての駅だったんですが、歳月の重みを感じさせる実に風情がある古い駅です。
駅舎はかなり古いようで、駅務室、窓口、改札口、待合室と並んでいます。



待合室が改札とは一体化しておらず、独立した作りになっているのが興味深いところ。寒さ対策なのかも知れません。



駅務室の照明が点いていたので覗いてみると、奥から駅員さんが。
この古い駅に日曜日の日中でも駅員さんがいるというのは、何とも嬉しくなります。
駅員さんの許しを得て、改札を通ってトイレへ。
トイレはつい最近新築されたばかりの真新しい建物で、男女それぞれのトイレの間に授乳スペースもあるユニバーサルトイレが設置されています。
市の補助があったのかも知れませんが、これはとても配慮が行き届いています。
武州荒木駅で待っていると、まず羽生方面から三峰口行きの列車がやってきました。
現行塗色の「1000系」です。
この駅では通常の駅とは逆で、進行方向右側の番線に進入してきます。



1~2分待っていると、今度は熊谷方面から羽生行きの列車が到着。
こちらは関西本線塗色の「1000系」です。
客人も無事到着。個人の墓所があるお寺に向かいました。
その後、別働隊の2人も現地で合流。
お墓参りを済ませた後、武州荒木駅で拾った客人は、午後に別用があるとのことで、再び武州荒木駅まで見送りに。


羽生からやって来た列車は、今度はヘッドマークを掲げた前塗色(現行塗色の前にまとっていた、黄色地に茶帯)の「1000系」でした。
大人4人、子ども2人の見送りを受けて、客人は去っていきました。
その後、故人のご実家へ。
到着するや否や、ご実家のお母さんの手回しで宅配ピザが届き、皆でご馳走になりました。
今回さまざまなバリエーションの塗色を目撃した秩父鉄道の「1000系」電車。
元々は国鉄「101系」電車でしたが、秩父鉄道の旧型車両を置き換えるために譲渡・改造のうえで入線してきました。
数の上では現時点(2010年4月26日)でも秩父鉄道の主力車両で、1編成は3両、両端の先頭車は冷房化改造を受けています(中間車は非冷房のまま)。
2007年には、さいたま市に「鉄道博物館」がオープンしたことを記念して、4編成を「国鉄リバイバルカラー」に変更。
国鉄時代の「101系」(と、改良型の「103系」)がまとったことがある4種類のカラーリング(京浜東北線のスカイブルー、総武線のカナリアイエロー、中央線のオレンジバーミリオン、関西本線のウグイス+先頭に黄帯)に変更。
さらに、1編成を前塗色(黄色地に茶帯)、もう1編成を旧塗色(茶のツートンカラー)に変更。
何とも心憎い演出です。
「1000系」が秩父鉄道に来てから約20年。
しかし、製造は40年以上前という老兵で、そろそろ後継車両との置き換えが必要になっていました。
そこで、東急電鉄で不要となった車両(まだまだ使えるものの、後継車両を導入することになったので玉突きで不要となった)を譲り受けることになりました。
まず昨年(2009年)、東急田園都市線で走っていた「8500系」が秩父鉄道の「7000系」として3両編成に改造され、2編成が入線してきました。
今年(2010年)に入ってからは、東急大井町線で活躍していた「8090系」が秩父鉄道の「7500系」として入線しています(4月26日現在、3両1編成)。
今後は後継車と置き換わることで年々数を減らしていく「1000系」。
かつて新性能電車の第一弾としてデビューした元国電「101系」ですが、今や現役で走る姿を見ることができるのは秩父鉄道だけとなりました。
近年中に、東急からの車両で置き換えられ、姿を消すことになるものと思います。
乗車や撮影は、全廃が決まってからでなく、お早めにどうぞ。
SL列車「パレオエクスプレス」が走り、風情がある駅舎も残る秩父鉄道。
その一方で、地方路線としては運行頻度が高く、有料急行の運行も行うなど、乗客の利便性もしっかり確保している鉄道でもあります。
(高頻度運転を行うJRや私鉄の幹線しか利用したことがない人には意外でしょうが、1時間に2~3本列車が走る路線は「かなり頑張っている路線」なんですよ!!)
週末などお時間があるとき、ちょっと足を伸ばして秩父鉄道に乗ってみませんか。
雲一つない晴天で、この季節らしい暖かさが戻る絶好の日和でした。
墓参には我が家と故人の後輩達が参加。
我が家はクルマで出かけ、先日数年ぶりで連絡が取れた故人の後輩の1人を秩父鉄道・武州荒木駅でピックアップし、お寺へ向かう段取り。
途中、朝食を仕入れたりトイレ休憩したり、買い物したりしながら、合流地点の武州荒木駅には、11:20過ぎに到着。
実際に訪れるのは初めての駅だったんですが、歳月の重みを感じさせる実に風情がある古い駅です。
駅舎はかなり古いようで、駅務室、窓口、改札口、待合室と並んでいます。
待合室が改札とは一体化しておらず、独立した作りになっているのが興味深いところ。寒さ対策なのかも知れません。
駅務室の照明が点いていたので覗いてみると、奥から駅員さんが。
この古い駅に日曜日の日中でも駅員さんがいるというのは、何とも嬉しくなります。
駅員さんの許しを得て、改札を通ってトイレへ。
トイレはつい最近新築されたばかりの真新しい建物で、男女それぞれのトイレの間に授乳スペースもあるユニバーサルトイレが設置されています。
市の補助があったのかも知れませんが、これはとても配慮が行き届いています。
武州荒木駅で待っていると、まず羽生方面から三峰口行きの列車がやってきました。
現行塗色の「1000系」です。
この駅では通常の駅とは逆で、進行方向右側の番線に進入してきます。
1~2分待っていると、今度は熊谷方面から羽生行きの列車が到着。
こちらは関西本線塗色の「1000系」です。
客人も無事到着。個人の墓所があるお寺に向かいました。
その後、別働隊の2人も現地で合流。
お墓参りを済ませた後、武州荒木駅で拾った客人は、午後に別用があるとのことで、再び武州荒木駅まで見送りに。
羽生からやって来た列車は、今度はヘッドマークを掲げた前塗色(現行塗色の前にまとっていた、黄色地に茶帯)の「1000系」でした。
大人4人、子ども2人の見送りを受けて、客人は去っていきました。
その後、故人のご実家へ。
到着するや否や、ご実家のお母さんの手回しで宅配ピザが届き、皆でご馳走になりました。
今回さまざまなバリエーションの塗色を目撃した秩父鉄道の「1000系」電車。
元々は国鉄「101系」電車でしたが、秩父鉄道の旧型車両を置き換えるために譲渡・改造のうえで入線してきました。
数の上では現時点(2010年4月26日)でも秩父鉄道の主力車両で、1編成は3両、両端の先頭車は冷房化改造を受けています(中間車は非冷房のまま)。
2007年には、さいたま市に「鉄道博物館」がオープンしたことを記念して、4編成を「国鉄リバイバルカラー」に変更。
国鉄時代の「101系」(と、改良型の「103系」)がまとったことがある4種類のカラーリング(京浜東北線のスカイブルー、総武線のカナリアイエロー、中央線のオレンジバーミリオン、関西本線のウグイス+先頭に黄帯)に変更。
さらに、1編成を前塗色(黄色地に茶帯)、もう1編成を旧塗色(茶のツートンカラー)に変更。
何とも心憎い演出です。
「1000系」が秩父鉄道に来てから約20年。
しかし、製造は40年以上前という老兵で、そろそろ後継車両との置き換えが必要になっていました。
そこで、東急電鉄で不要となった車両(まだまだ使えるものの、後継車両を導入することになったので玉突きで不要となった)を譲り受けることになりました。
まず昨年(2009年)、東急田園都市線で走っていた「8500系」が秩父鉄道の「7000系」として3両編成に改造され、2編成が入線してきました。
今年(2010年)に入ってからは、東急大井町線で活躍していた「8090系」が秩父鉄道の「7500系」として入線しています(4月26日現在、3両1編成)。
今後は後継車と置き換わることで年々数を減らしていく「1000系」。
かつて新性能電車の第一弾としてデビューした元国電「101系」ですが、今や現役で走る姿を見ることができるのは秩父鉄道だけとなりました。
近年中に、東急からの車両で置き換えられ、姿を消すことになるものと思います。
乗車や撮影は、全廃が決まってからでなく、お早めにどうぞ。
SL列車「パレオエクスプレス」が走り、風情がある駅舎も残る秩父鉄道。
その一方で、地方路線としては運行頻度が高く、有料急行の運行も行うなど、乗客の利便性もしっかり確保している鉄道でもあります。
(高頻度運転を行うJRや私鉄の幹線しか利用したことがない人には意外でしょうが、1時間に2~3本列車が走る路線は「かなり頑張っている路線」なんですよ!!)
週末などお時間があるとき、ちょっと足を伸ばして秩父鉄道に乗ってみませんか。
【オススメ】鉄道ファン2010年6月号
- 2010/04/25 (Sun)
- オススメ(書籍・雑誌) |
- TB() |
- CM(0) |
- Edit |
- ▲Top
月刊「鉄道ファン」の最新号。
今回の特集は「新幹線開業前夜」。
東北新幹線の新青森開業と、九州新幹線鹿児島ルートの全線開業を目前にして、これまでの各新幹線が開業するのに合わせて、在来線にはどんな影響が生じていたのか、また目前に迫った東北・九州両親幹線の延伸によりどんな影響が生じるのか……など、詳細に分析。
「新車ガイド」では、ハイブリッド入替機関車「HD300形」、JR北海道初のアルミ車体電車「735系」、JR西日本の特急形気動車「キハ189系」、JR東日本の京葉線向け新型車両「E233系5000番台」などを紹介。
ほかに、先のダイヤ改正で廃止となった寝台特急「北陸」、季節列車に格下げとなった夜行急行「能登」、ついに引退となった「キハ52形」などの記事も。
「サイクルトレインで遊ぼう!」という企画記事は、今回なんと関東鉄道常総線が題材。
常総線は、日中の時間帯であれば、折り畳めない自転車でも車内持ち込みが行えるので(大田郷~水海道駅間/持ち込めるのは、9:30~14:30の間に乗車する列車に限る)、「うまく活用すると、こんな利用方法もありますよ」という提案ともなっています。
なお、記事では真岡鐵道の茂木駅にも足を伸ばしていますが、脚注にもあるように、真岡鐵道ではサイクルトレインの運行は行っていないので、その点はご注意を(記事では折り畳み自転車を畳んだ状態で持ち込んでいる?ようです)。
今回の特集は「新幹線開業前夜」。
東北新幹線の新青森開業と、九州新幹線鹿児島ルートの全線開業を目前にして、これまでの各新幹線が開業するのに合わせて、在来線にはどんな影響が生じていたのか、また目前に迫った東北・九州両親幹線の延伸によりどんな影響が生じるのか……など、詳細に分析。
「新車ガイド」では、ハイブリッド入替機関車「HD300形」、JR北海道初のアルミ車体電車「735系」、JR西日本の特急形気動車「キハ189系」、JR東日本の京葉線向け新型車両「E233系5000番台」などを紹介。
ほかに、先のダイヤ改正で廃止となった寝台特急「北陸」、季節列車に格下げとなった夜行急行「能登」、ついに引退となった「キハ52形」などの記事も。
「サイクルトレインで遊ぼう!」という企画記事は、今回なんと関東鉄道常総線が題材。
常総線は、日中の時間帯であれば、折り畳めない自転車でも車内持ち込みが行えるので(大田郷~水海道駅間/持ち込めるのは、9:30~14:30の間に乗車する列車に限る)、「うまく活用すると、こんな利用方法もありますよ」という提案ともなっています。
なお、記事では真岡鐵道の茂木駅にも足を伸ばしていますが、脚注にもあるように、真岡鐵道ではサイクルトレインの運行は行っていないので、その点はご注意を(記事では折り畳み自転車を畳んだ状態で持ち込んでいる?ようです)。
鉄道ファン2010年6月号 【発行】交友社 【ジャンル】鉄道月刊誌 【発売日】2010年4月21日 【税込価格】1,100円 【判型】B5判 【備考】 |
【レポート】2010年4月定例運転会
2010年4月17日(土)~18日(日)、「アルテリオ」での定例運転会を開催しました。
会場は「アルテリオ」2Fの「研修室」。
一般の見学者だけでなく、市の職員の方も休憩時間にお見えになっていました。
今回は、スノコを活用した高架路線を初投入。
これを利用すると、机を離しても線路を接続できるので「島」内部への通路を設けることができるのと、机同士に段差があっても間を開けることで容易に克服できることが分かり、思わぬ収穫となりました。



なお、17日(土)は私のみ、18日(日)は「ソロモンの悪夢」さんと、途中から「ゆうちゃん」さんが参加。終了間際には「たひ」さんも到着し、撤収作業と、打ち上げに参加しました。
【参加メンバー】(50音順)
・「ソロモンの悪夢」氏
・「たひ」氏(撤収作業から参加)
・「ゆうちゃん」氏
・管理人(私)一家(チビ怪獣・プチ怪獣も)
■Nゲージには「スノコ高架」を投入
今回は事前に参加者が少ないこと(=モジュールの持ち込みが難しいこと)が分かっていたので、以前から考えていたプランを実行。
まず、ホームセンターで販売しているスノコ(天板は4枚の桐製/2枚セットで398円)を天板1枚ごとに「分解」。
それに100円ショップで販売している工作用の角材を、両端付近に接着。
固着した後、天板の上に線路を乗せれば、高架路線の出来上がりです。



スノコの天板の幅は、KATOの高架線路を乗せるのにちょうど良いうえ、長さが約75cmでKATO線路3枚分に相当するという、なんとも都合の良いサイズ。
これは利用しない手はない……というわけです。
本来の高架線路は、橋脚部分と線路プレート部分の組み立てと解体が案外面倒で、毎回かなり時間を要していました。
また、そのまま組み立てても、当方モジュール規格とは高さがかなり異なるため、かさ上げをしなければならず、その調整にも毎回かなりの時間を要していました。



スノコ高架線があれば、KATOの高架プレートをそのまま乗せることができるので、設置・撤収に要する時間はかなり短縮できます。
なおかつ、接着した橋脚を支点とすることで、机と机の間を50cm以上離して設置できるようになったため、そのすき間を通路として利用できるように。
これまでは会議机で作った「島」の中に入るには、机の下をくぐるしかなく難儀していたので、これは大きな進歩です。
また、机に段差があっても、50cmも離せばほとんど問題ないレベルになるため、その点でも大きな収穫となりました。
■HOゲージは長大編成も/トーマス見参
HOゲージは、「ソロモンの悪夢」さんがお手持ちのさまざまな車両を展開。
アメリカ型長大編成が豪快なDCCサウンドを鳴り響かせて快走。
途中からは「ゆうちゃん」さんも「参戦」し、お二人の車両でかなり盛大な状況となりました。
私もドイツ型車両などを若干持ち込んではいたのですが、Nゲージの「土木作業」に時間を取られて展開できずじまい。
HOについても、Nゲージでスノコ高架が効果的であったことを踏まえ、今後はスノコ地盤を投入してみようか……という話も。
「全線」は無理にしても、通路を設ける部分だけでもスノコを入れることが出来れば……(前後の高さ調整は必要になりますが)。
ちなみに、スノコの天板はHOスケールのプラットホームにもうってつけで、ちょっと手を加えれば立派なホームに早変わりしそうです。



なお、今回はバックマン製の「きかんしゃトーマス」も見参(英国型なので「OOゲージ」)。
「きかんしゃトーマス」ベーシックセットには、トーマスと2両の客車達、円が描ける分のカーブレール、バックマンのパワーパックが同梱。
某ショップで処分品として叩き売られていたものを思い切って購入したもので、7,000円しませんでした。
トーマスは「目が動く」というギミックを搭載しているので、我が家の怪獣軍団も大喜び。
実は当会最初の運転会で「駿くんパパ」さんが同社のトーマスを持ち込んでいますが、こちらはなんとDCC化済み。
スモーク機能まで仕込もうとすると、目が動かせなくなる(機器が干渉するのでしょう)んだそうで……。
■打ち上げは今回も「爆弾ハンバーグ」
今回は日曜日の撤収作業が終わった後、いつものようには「フライングガーデン」で打ち上げ。
途中から参加した「たひ」さんも含め、大人4人が怪しい改造話やら危険なショップ話やらで盛り上がっていました。
なお、次回の開催は2010年5月15日(土)~16日(日)、会場は「研修室」です。
(15日は前日設営&試運転)
会場は「アルテリオ」2Fの「研修室」。
一般の見学者だけでなく、市の職員の方も休憩時間にお見えになっていました。
今回は、スノコを活用した高架路線を初投入。
これを利用すると、机を離しても線路を接続できるので「島」内部への通路を設けることができるのと、机同士に段差があっても間を開けることで容易に克服できることが分かり、思わぬ収穫となりました。
なお、17日(土)は私のみ、18日(日)は「ソロモンの悪夢」さんと、途中から「ゆうちゃん」さんが参加。終了間際には「たひ」さんも到着し、撤収作業と、打ち上げに参加しました。
【参加メンバー】(50音順)
・「ソロモンの悪夢」氏
・「たひ」氏(撤収作業から参加)
・「ゆうちゃん」氏
・管理人(私)一家(チビ怪獣・プチ怪獣も)
■Nゲージには「スノコ高架」を投入
今回は事前に参加者が少ないこと(=モジュールの持ち込みが難しいこと)が分かっていたので、以前から考えていたプランを実行。
まず、ホームセンターで販売しているスノコ(天板は4枚の桐製/2枚セットで398円)を天板1枚ごとに「分解」。
それに100円ショップで販売している工作用の角材を、両端付近に接着。
固着した後、天板の上に線路を乗せれば、高架路線の出来上がりです。
スノコの天板の幅は、KATOの高架線路を乗せるのにちょうど良いうえ、長さが約75cmでKATO線路3枚分に相当するという、なんとも都合の良いサイズ。
これは利用しない手はない……というわけです。
本来の高架線路は、橋脚部分と線路プレート部分の組み立てと解体が案外面倒で、毎回かなり時間を要していました。
また、そのまま組み立てても、当方モジュール規格とは高さがかなり異なるため、かさ上げをしなければならず、その調整にも毎回かなりの時間を要していました。
スノコ高架線があれば、KATOの高架プレートをそのまま乗せることができるので、設置・撤収に要する時間はかなり短縮できます。
なおかつ、接着した橋脚を支点とすることで、机と机の間を50cm以上離して設置できるようになったため、そのすき間を通路として利用できるように。
これまでは会議机で作った「島」の中に入るには、机の下をくぐるしかなく難儀していたので、これは大きな進歩です。
また、机に段差があっても、50cmも離せばほとんど問題ないレベルになるため、その点でも大きな収穫となりました。
■HOゲージは長大編成も/トーマス見参
HOゲージは、「ソロモンの悪夢」さんがお手持ちのさまざまな車両を展開。
アメリカ型長大編成が豪快なDCCサウンドを鳴り響かせて快走。
途中からは「ゆうちゃん」さんも「参戦」し、お二人の車両でかなり盛大な状況となりました。
私もドイツ型車両などを若干持ち込んではいたのですが、Nゲージの「土木作業」に時間を取られて展開できずじまい。
HOについても、Nゲージでスノコ高架が効果的であったことを踏まえ、今後はスノコ地盤を投入してみようか……という話も。
「全線」は無理にしても、通路を設ける部分だけでもスノコを入れることが出来れば……(前後の高さ調整は必要になりますが)。
ちなみに、スノコの天板はHOスケールのプラットホームにもうってつけで、ちょっと手を加えれば立派なホームに早変わりしそうです。
なお、今回はバックマン製の「きかんしゃトーマス」も見参(英国型なので「OOゲージ」)。
「きかんしゃトーマス」ベーシックセットには、トーマスと2両の客車達、円が描ける分のカーブレール、バックマンのパワーパックが同梱。
某ショップで処分品として叩き売られていたものを思い切って購入したもので、7,000円しませんでした。
トーマスは「目が動く」というギミックを搭載しているので、我が家の怪獣軍団も大喜び。
実は当会最初の運転会で「駿くんパパ」さんが同社のトーマスを持ち込んでいますが、こちらはなんとDCC化済み。
スモーク機能まで仕込もうとすると、目が動かせなくなる(機器が干渉するのでしょう)んだそうで……。
■打ち上げは今回も「爆弾ハンバーグ」
今回は日曜日の撤収作業が終わった後、いつものようには「フライングガーデン」で打ち上げ。
途中から参加した「たひ」さんも含め、大人4人が怪しい改造話やら危険なショップ話やらで盛り上がっていました。
なお、次回の開催は2010年5月15日(土)~16日(日)、会場は「研修室」です。
(15日は前日設営&試運転)
【富山地鉄】新型LRV「T100形」が試運転開始
- 2010/04/23 (Fri)
- ニュース(鉄道・LRT・バスなど) |
- TB() |
- CM(0) |
- Edit |
- ▲Top
JRの在来線をLRT化した「富山ライトレール」の成功や、富山市中心街の路面電車を環状線化した「セントラム」の開業など、LRTや路面電車の先進都市になっている富山。
その富山市内を走る富山地方鉄道(富山地鉄)の市内軌道線用の新型車両「T100形」が試運転を開始しました。
3連接車体の低床型LRVで、先年豊橋鉄道が導入した「T1000形」と準同形車です。
2010年4月28日から営業運転に投入する予定のようです。
・富山地方鉄道T100形が試運転(「railf.jp」 2010年4月21日)
http://railf.jp/news/2010/04/22/175300.html
・富山地方鉄道が新車両、小回り利く3両編成(読売新聞 2010年4月17日)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100417-OYT1T00071.htm
・路面電車 若返る 地鉄 南富山―富山で28日から(中日新聞 2010年4月17日)
http://www.chunichi.co.jp/article/toyama/20100417/CK2010041702000147.html?ref=rank
市内環状線用のセントラム用「9000形」が、富山ライトレールの「TLR0600形」(ポートラム)と同形の2連接車体であったのに対し、今回の車両は3連接の車両ということが興味深い点です。
なぜ、2連接車と3連接車を同時並行的に導入するようになるのか。
これはおそらく、富山駅の高架化事業が終わった後を見据えたことで、富山ライトレールとセントラムの直通運転と、市内軌道線との「誤乗防止」も企図しているのだろうと思います。
富山駅の高架化が実現すると、高架下に軌道を新設して、駅北口の富山ライトレールと駅南口の富山地鉄市内線が高架下をくぐって直通運転(この区間は軌道を新設)を行う計画があります。
そうなれば、おそらく富山ライトレールとセントラムが直通運転(一体運用)を行うようになるのではないでしょうか。
つまり、富山ライトレールの電車は、富山駅から地鉄の市内線に入り、セントラムと同じルートで市街地をぐるっと1周して富山駅に戻り、再び富山ライトレールの岩瀬浜方面に戻る運用を想定しているではないか……と思います。
このため、セントラムは富山ライトレールとの共通運転を前提に富山ライトレールと同形車を導入したのでしょう。
一方、富山ライトレール側への乗り入れを行う予定がない既存の地鉄市内軌道線については、あえて同形車にする必然性はなく、であれば誤乗防止にもなるので、異なる車両を導入すれば良いのではないか……ということになったのだろうと思います。
ちなみに、セントラムの「9000形」や富山ライトレールの「TLR0600形」は新潟トランシス製、「T100形」はアルナ車両製です。
今回の「T100形」も豊橋鉄道の「T1000形」も、アルナ車両が展開するLRV「リトルダンサー」シリーズの「U」タイプを狭軌用とした「Ua」タイプです。
台車がない部分の床の高さは、地上から38cm。
台車がある部分の床の高さは、地上から48cm。
車軸付きという在来構造の車両ながら、100%低床を実現しています。
「リトルダンサー」シリーズの特徴は、低床車でありながら、台車は「車軸レス構造ではない」こと。
(セントラムやポートラムは「車軸レス構造」、つまり車輪間の車軸がないことで低床化を実現している)
在来構造なのでで、車軸レス構造に比べると保守点検が容易であるというメリットがあります。
ともあれ、今回の「T100形」の導入が進めば、やがて路面電車然としたスタイルの「7000形」は淘汰されるはず。
富山の街中の風景は、次第に変わっていくのでしょうね。
その富山市内を走る富山地方鉄道(富山地鉄)の市内軌道線用の新型車両「T100形」が試運転を開始しました。
3連接車体の低床型LRVで、先年豊橋鉄道が導入した「T1000形」と準同形車です。
2010年4月28日から営業運転に投入する予定のようです。
・富山地方鉄道T100形が試運転(「railf.jp」 2010年4月21日)
http://railf.jp/news/2010/04/22/175300.html
・富山地方鉄道が新車両、小回り利く3両編成(読売新聞 2010年4月17日)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100417-OYT1T00071.htm
・路面電車 若返る 地鉄 南富山―富山で28日から(中日新聞 2010年4月17日)
http://www.chunichi.co.jp/article/toyama/20100417/CK2010041702000147.html?ref=rank
市内環状線用のセントラム用「9000形」が、富山ライトレールの「TLR0600形」(ポートラム)と同形の2連接車体であったのに対し、今回の車両は3連接の車両ということが興味深い点です。
なぜ、2連接車と3連接車を同時並行的に導入するようになるのか。
これはおそらく、富山駅の高架化事業が終わった後を見据えたことで、富山ライトレールとセントラムの直通運転と、市内軌道線との「誤乗防止」も企図しているのだろうと思います。
富山駅の高架化が実現すると、高架下に軌道を新設して、駅北口の富山ライトレールと駅南口の富山地鉄市内線が高架下をくぐって直通運転(この区間は軌道を新設)を行う計画があります。
そうなれば、おそらく富山ライトレールとセントラムが直通運転(一体運用)を行うようになるのではないでしょうか。
つまり、富山ライトレールの電車は、富山駅から地鉄の市内線に入り、セントラムと同じルートで市街地をぐるっと1周して富山駅に戻り、再び富山ライトレールの岩瀬浜方面に戻る運用を想定しているではないか……と思います。
このため、セントラムは富山ライトレールとの共通運転を前提に富山ライトレールと同形車を導入したのでしょう。
一方、富山ライトレール側への乗り入れを行う予定がない既存の地鉄市内軌道線については、あえて同形車にする必然性はなく、であれば誤乗防止にもなるので、異なる車両を導入すれば良いのではないか……ということになったのだろうと思います。
ちなみに、セントラムの「9000形」や富山ライトレールの「TLR0600形」は新潟トランシス製、「T100形」はアルナ車両製です。
今回の「T100形」も豊橋鉄道の「T1000形」も、アルナ車両が展開するLRV「リトルダンサー」シリーズの「U」タイプを狭軌用とした「Ua」タイプです。
台車がない部分の床の高さは、地上から38cm。
台車がある部分の床の高さは、地上から48cm。
車軸付きという在来構造の車両ながら、100%低床を実現しています。
「リトルダンサー」シリーズの特徴は、低床車でありながら、台車は「車軸レス構造ではない」こと。
(セントラムやポートラムは「車軸レス構造」、つまり車輪間の車軸がないことで低床化を実現している)
在来構造なのでで、車軸レス構造に比べると保守点検が容易であるというメリットがあります。
ともあれ、今回の「T100形」の導入が進めば、やがて路面電車然としたスタイルの「7000形」は淘汰されるはず。
富山の街中の風景は、次第に変わっていくのでしょうね。
【JR北海道】同社初のアルミ車「735系」電車が報道公開
- 2010/04/21 (Wed)
- ニュース(鉄道・LRT・バスなど) |
- TB() |
- CM(0) |
- Edit |
- ▲Top
北海道の話題ですが、気になったのでご紹介。
JR北海道は、同社初となるアルミ車体を採用した「735系」電車の報道公開を行いました。
(同じ銀地の車体でも、これまでにJR北海道が採用していたのはステンレス車でした)
夏季の間は「731系」電車と同様の営業運転に充当し、冬期は寒冷地でアルミ車体が十分な耐久性を持っているかどうかの「寒冷地試験」に供するようです。
・JR北海道初のアルミ車体735系誕生。(「編集長敬白」 2010年4月17日)
http://rail.hobidas.com/blog/natori/archives/2010/04/735.html
・735系が試運転を実施(「railf.jp」 2010年4月6日)
http://railf.jp/news/2010/04/07/200500.html
「735系」の「顔(先頭形状)」は、先輩である「731系」(及び「キハ201系」)と同様の、迫力ある引き締まったデザイン。
ドアの配置も「731系」と同じく片開き・3ドア。
車輪の直径が810mmと、従来の車両より小さくなったことで低床化を実現しています。
かつて北海道の車両は、冬期の寒気対策で必ずデッキがあり、二重扉と同じ要領で外気が直接車内に入ってこないようにしていたんですが、最近の通勤形車両はエアカーテンで外気が入ってくるのを抑制する仕組みになっていて、新造されるデッキ付きの車両は事実上特急形だけになっています。
北海道に旅行すると、札幌周辺でこの電車に出会うかも知れませんよ。
JR北海道は、同社初となるアルミ車体を採用した「735系」電車の報道公開を行いました。
(同じ銀地の車体でも、これまでにJR北海道が採用していたのはステンレス車でした)
夏季の間は「731系」電車と同様の営業運転に充当し、冬期は寒冷地でアルミ車体が十分な耐久性を持っているかどうかの「寒冷地試験」に供するようです。
・JR北海道初のアルミ車体735系誕生。(「編集長敬白」 2010年4月17日)
http://rail.hobidas.com/blog/natori/archives/2010/04/735.html
・735系が試運転を実施(「railf.jp」 2010年4月6日)
http://railf.jp/news/2010/04/07/200500.html
「735系」の「顔(先頭形状)」は、先輩である「731系」(及び「キハ201系」)と同様の、迫力ある引き締まったデザイン。
ドアの配置も「731系」と同じく片開き・3ドア。
車輪の直径が810mmと、従来の車両より小さくなったことで低床化を実現しています。
かつて北海道の車両は、冬期の寒気対策で必ずデッキがあり、二重扉と同じ要領で外気が直接車内に入ってこないようにしていたんですが、最近の通勤形車両はエアカーテンで外気が入ってくるのを抑制する仕組みになっていて、新造されるデッキ付きの車両は事実上特急形だけになっています。
北海道に旅行すると、札幌周辺でこの電車に出会うかも知れませんよ。
【川崎重工】次世代LRV「SWIMO」地球環境大賞を受賞/海外への輸出も
- 2010/04/19 (Mon)
- ニュース(鉄道・LRT・バスなど) |
- TB() |
- CM(0) |
- Edit |
- ▲Top
川崎重工が開発中の新型LRV(LRT用の車両)「SWIMO(スイモ)」が「第19回 地球環境大賞」を受賞し、4月8日に授賞式が行われたそうです。
また、現在は国内の基準に合わせて運転最高速度が40km/hとなっているのですが、これを80km/hに引き上げる輸出型の開発も始めるようです。
・北米仕様で海外へGO 電池駆動路面電車「SWIMO」 川崎重工(SankeiBiz 2010年4月7日)
http://www.sankeibiz.jp/business/news/100407/bsb1004072025011-n1.htm
・川崎重工 SWIMO地球環境大賞受賞と輸出始動(「路面電車とLRTを考える館」 2010年4月15日)
http://www.urban.ne.jp/home/yaman/news95.htm
「SWIMO」は、大容量ニッケル水素電池「ギガセル」を搭載し、急速充電可能で、架線がない区間でも走行できる3連接タイプの新型LRV。
3~5分の充電時間で10km程度は走れるので、電停(停留所)部分だけ架線を張り、それ以外の区間は架線レスにしても走行可能です。
また、既存の鉄道へ乗り入れる場合も同様のことがいえ、例えば非電化路線であっても駅部分だけに架線を張り、停車中に急速充電を行うようにすれば、最低限の投資額で十分な効果を得ることができるでしょう。
日本では欧州のようなトラムトレイン(郊外の鉄道路線と、市街地の路面電車の軌道を直通する列車)はまだ一般的ではありませんが(かつて名鉄が行っていた鉄軌直通列車や、広島電鉄の市内線・宮島線直通運転がこれに近い)、今後こうした運転形態が普及すると、「SWIMO」や、鉄道総研が開発中の「Hi-tram」のような車両は重宝されるようになると思います。
あとは「ギガセル」が十分な実用レベルに達しているかどうか(やや語弊がありますが「武人の蛮用に耐え得る」レベルかどうか)という点と、普及に必要な「お手頃価格帯」に下がるかどうかという点が課題となるでしょうね。
また、現在は国内の基準に合わせて運転最高速度が40km/hとなっているのですが、これを80km/hに引き上げる輸出型の開発も始めるようです。
・北米仕様で海外へGO 電池駆動路面電車「SWIMO」 川崎重工(SankeiBiz 2010年4月7日)
http://www.sankeibiz.jp/business/news/100407/bsb1004072025011-n1.htm
・川崎重工 SWIMO地球環境大賞受賞と輸出始動(「路面電車とLRTを考える館」 2010年4月15日)
http://www.urban.ne.jp/home/yaman/news95.htm
「SWIMO」は、大容量ニッケル水素電池「ギガセル」を搭載し、急速充電可能で、架線がない区間でも走行できる3連接タイプの新型LRV。
3~5分の充電時間で10km程度は走れるので、電停(停留所)部分だけ架線を張り、それ以外の区間は架線レスにしても走行可能です。
また、既存の鉄道へ乗り入れる場合も同様のことがいえ、例えば非電化路線であっても駅部分だけに架線を張り、停車中に急速充電を行うようにすれば、最低限の投資額で十分な効果を得ることができるでしょう。
日本では欧州のようなトラムトレイン(郊外の鉄道路線と、市街地の路面電車の軌道を直通する列車)はまだ一般的ではありませんが(かつて名鉄が行っていた鉄軌直通列車や、広島電鉄の市内線・宮島線直通運転がこれに近い)、今後こうした運転形態が普及すると、「SWIMO」や、鉄道総研が開発中の「Hi-tram」のような車両は重宝されるようになると思います。
あとは「ギガセル」が十分な実用レベルに達しているかどうか(やや語弊がありますが「武人の蛮用に耐え得る」レベルかどうか)という点と、普及に必要な「お手頃価格帯」に下がるかどうかという点が課題となるでしょうね。
「クルマ大国」栃木でもパーク&ライドが普及
- 2010/04/16 (Fri)
- ニュース(鉄道・LRT・バスなど) |
- TB() |
- CM(0) |
- Edit |
- ▲Top
産経新聞(のweb版「MSN産経ニュース」)栃木版に、栃木県内におけるパーク&ライドの普及状況についての記事が掲載されました。
広がりつつあるこの動きの先に、「もう一段の動き」を期待したいところです。
・渋滞緩和、環境保全 「パーク・アンド・ライド」広がる 栃木(MSN産経ニュース 2010年4月15日 2:52)
http://sankei.jp.msn.com/region/kanto/tochigi/100415/tcg1004150252000-n1.htm
クルマ依存が顕著な栃木県でも、こうした動きが少しずつ普及しつつあるというのは興味深いところです。
クルマは確かに圧倒的に便利なんですが(そりゃそうです)、だからといって皆が一斉にクルマを使ってしまうと、必然的に渋滞の頻発という事態を招きます。
観光地の渋滞は、まさにその典型です。
記事でも触れていますが、昨年秋の行楽シーズンの際、那須の茶臼岳方面へ向かう登山道路の一般車通行を禁止して、パーク&ライド用駐車場からシャトルバスに乗り換えてもらうという社会実験が行われました。
自家用車を規制した結果、目立った渋滞は発生せず、例年だと大渋滞で身動きが取れなくなる料金所から山頂までの所要時間は、通常の行楽シーズンより50分も短かくて済んだそうです。
観光地に限らず、パーク&ライドは行われています。
各鉄道では駅に駐車場を設けてパーク&ライドを行っていて、年々利用者が増えています。
行き先にもよりますが、直接目的地に向かうよりも、途中から列車で移動した方が、時間が読めて良い……ということは結構あります。
これまでの動きは、既存の鉄道・バスとの連携がメインでした。
つまり、今回の記事で紹介されているような事例です。
「やっと」の感もありますが、こうした動きが広がりつつあることは歓迎すべきでしょうね。
これからの動きは、新規の公共交通の開業を含めた公共交通ネットワークの構築や再編。
既存の鉄道・バスとの連携はもちろん、必要であればLRT路線新設などを含む積極策を推進していく……ということになるでしょうね。
広がりつつあるこの動きの先に、「もう一段の動き」を期待したいところです。
・渋滞緩和、環境保全 「パーク・アンド・ライド」広がる 栃木(MSN産経ニュース 2010年4月15日 2:52)
http://sankei.jp.msn.com/region/kanto/tochigi/100415/tcg1004150252000-n1.htm
クルマ依存が顕著な栃木県でも、こうした動きが少しずつ普及しつつあるというのは興味深いところです。
クルマは確かに圧倒的に便利なんですが(そりゃそうです)、だからといって皆が一斉にクルマを使ってしまうと、必然的に渋滞の頻発という事態を招きます。
観光地の渋滞は、まさにその典型です。
記事でも触れていますが、昨年秋の行楽シーズンの際、那須の茶臼岳方面へ向かう登山道路の一般車通行を禁止して、パーク&ライド用駐車場からシャトルバスに乗り換えてもらうという社会実験が行われました。
自家用車を規制した結果、目立った渋滞は発生せず、例年だと大渋滞で身動きが取れなくなる料金所から山頂までの所要時間は、通常の行楽シーズンより50分も短かくて済んだそうです。
観光地に限らず、パーク&ライドは行われています。
各鉄道では駅に駐車場を設けてパーク&ライドを行っていて、年々利用者が増えています。
行き先にもよりますが、直接目的地に向かうよりも、途中から列車で移動した方が、時間が読めて良い……ということは結構あります。
これまでの動きは、既存の鉄道・バスとの連携がメインでした。
つまり、今回の記事で紹介されているような事例です。
「やっと」の感もありますが、こうした動きが広がりつつあることは歓迎すべきでしょうね。
これからの動きは、新規の公共交通の開業を含めた公共交通ネットワークの構築や再編。
既存の鉄道・バスとの連携はもちろん、必要であればLRT路線新設などを含む積極策を推進していく……ということになるでしょうね。
カレンダー
カテゴリー
最新記事
(02/18)
(02/15)
(02/11)
(02/06)
(02/05)
(02/03)
(01/29)
(01/26)
(01/26)
(01/12)
(12/08)
(11/18)
(11/10)
(10/18)
(09/19)
プロフィール
HN:
下館レイル倶楽部・代表
性別:
男性
趣味:
鉄道、鉄道模型、ミリタリーなど
自己紹介:
「下館レイル倶楽部」は、鉄道の街・下館(茨城県筑西市)を中心に活動する鉄道&鉄道模型の趣味団体です。
しもだて地域交流センター「アルテリオ」で鉄道模型の運転会を毎月開催するほか、各種イベントの見学・撮影なども実施しています。
公共交通の上手な利活用や、鉄道など公共交通を活かしたまちづくりなどの情報発信も行います!
・mixi(ミクシィ)
・Facebook(フェイスブック)
・Twitter(ツイッター)
・ご連絡&お問い合わせメールアドレス
nal@sainet.or.jp(←「@」を半角文字にしてお送りください)
しもだて地域交流センター「アルテリオ」で鉄道模型の運転会を毎月開催するほか、各種イベントの見学・撮影なども実施しています。
公共交通の上手な利活用や、鉄道など公共交通を活かしたまちづくりなどの情報発信も行います!
・mixi(ミクシィ)
・Facebook(フェイスブック)
・Twitter(ツイッター)
・ご連絡&お問い合わせメールアドレス
nal@sainet.or.jp(←「@」を半角文字にしてお送りください)
ブログ内検索
アーカイブ
カウンター
リンク
最新コメント
[09/08 水戸光圀]
[08/24 妄想鉄道君]
[05/16 さにぼー]
[03/30 ガーゴイル]
[02/16 管理人]
[02/12 FUKU]
[01/15 伊東 尚]
[02/20 GOO]
[07/27 NAL(管理人)]
[07/12 風旅記]
最新トラックバック
最古記事
(06/12)
(06/12)
(06/21)
(07/24)
(08/10)
(08/10)
(08/18)
(08/26)
(09/01)
(09/15)
(10/11)
(10/14)
(10/22)
(10/29)
(10/29)